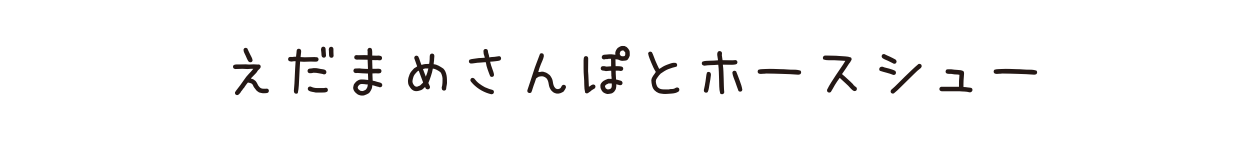丸くころころした体型の猫は可愛いですよね。
しかし「肥満は万病のもと」というように、猫も太りすぎてしまうと様々な健康被害をもたらす原因になります。
可愛い愛猫に一日でも長く健やかに過ごしてもらうために、標準的な体重と体型を維持することも非常に重要になってきます。
そこで今回は、猫が肥満になる原因とそのリスクについて詳しくご紹介します。
猫の肥満について【太るきっかけ】

成長期の子猫は非常によく遊び、体も毎日成長するので大量のエネルギーが消費されます。
子猫用のフードを見てみると、高カロリーであることに気がつきます。
子猫はそれだけ毎日、大量のエネルギーを消費しながら成長しているということなのです。
では、猫が太りはじめるきっかけにはどのようなものがあるのでしょうか?
詳しくみていきましょう!
年齢によるもの

猫はシニア世代に近づくと子猫のように激しく遊ばなくなり、一日のほとんどを寝ているかのんびりと寛いで過ごします。
代謝も落ちてくるため、それに比例するように脂肪もつきやすくなっていきます。
去勢・避妊手術によるもの
去勢や避妊手術も太りやすくなるきっかけといわれています。
去勢・避妊手術によってホルモンのバランスが変わります。
そのため、基礎代謝が低下してしまうことがあり、太りやすくなってしまうのです。
体質によるもの
人に太りやすい体質の人がいるように、猫にも太りやすい体質の子がいます。
フードの量を適切に守っていて、定期的に運動をさせていても太ってしまうのです。
食べ過ぎによるもの

フードやおやつを食べすぎていると太り気味になってしまします。
多頭飼いをしている場合、他の猫のフードも食べてしまい太ってしまうことがあります。

まさにうちの まめがそれであると考えらます。
運動不足によるもの
完全室内飼いの場合、安全な家の中でのんびりと過ごす時間が長くなり
運動量が不足して太りやすくなるきっかけになります。
人の食べ物を与えていることによるもの

人の食べ物に興味をしめす猫も多いと思います。
愛猫の可愛いおねだりに負けて、人の食べ物を与えると太りやすくなります。
人の食べ物は猫にとって非常に高カロリーなので、あっという間に肥満体型になるという危険性があります。
また、カロリーだけではなく塩分量なども猫にとっては多いので、人の食べ物は与えないようにしましょう。
病気や怪我によるもの
病気や怪我がきっかけで太りやすくなってしまうこともあります。
甲状腺機能低下症やクッシング症候群といった内分泌に異常が出る病気がきっかけで、太りやすくなります。
また、脚などを怪我すると必然的に運動量が減り、太るきっかけになります。
猫の肥満について【猫の肥満によるリスク】

肥満には様々なリスクが伴います。
猫の肥満とされる数値は、適正体重の15%増からとされ、この15%を超えると体の不調が発生するといわれています。
特に病気を発症しやすくなるので、注意が必要です。
肥満により発生のリスクが高まる病気は以下のものが挙げられます。
- 糖尿病
- 関節炎
- 心臓病
- 肝リピドーシス
- 下部尿路疾患
- 皮膚病
肥満で皮膚病?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
皮下脂肪が増えると、皮膚への栄養血管に負担がかかることで皮膚病になりやすくなったり、傷の治りが遅くなることがあります。
また、猫自身が動くことが億劫になってしまい、毛繕いをしなくなると雑菌などが繁殖し、それが原因で皮膚病になる可能性も考えられます。
その他にも、便秘になりやすくなったり、腫瘍ができやすくなるといわれています。
ころころした猫は見た目に可愛いですが、上記のようにたくさんのリスクが伴います。
笑い事では済まない事態になることもるため注意が必要です。
猫の肥満について【 太った猫への注意点 】

万が一、愛猫が肥満になってしまった場合、いつも通りの生活を送らせることにもリスクが伴うので注意が必要です。
丸まるとした猫は体を丸めることができず、毛繕いが困難になってくる場合があります。
その場合、雑菌が繁殖して皮膚病になるリスクが高まるため、飼い主さんが体のケアをしてあげましょう。
固く絞ったタオルやシャンプータオルなどで拭き、体を清潔に保ってあげることが大切です。
その他に、無理なジャンプや高いところからの飛び降りなどにも注意が必要です。
着地の衝撃は背骨や椎間板、脚の関節にダメージを与え、脱臼や骨折、靭帯の負傷の危険性があります。
高いところへ移動することがある場合は、スロープや踏み台を設置してあげましょう。
猫の肥満について【 さいごに 】

「肥満は万病のもと」これは人も猫も同じです。
猫のダイエット(肥満治療)は長い時間が必要になります。
糖尿病になれば薬代がかかります。
愛猫を太らせないためには、フード量を適切に保ち、定期的な体重測定をして飼い主さんがきちんと健康管理をしてあげましょう。
愛猫が太ってしまったからといってフード量を極端に減らしたりなどの無理なダイエットは禁物です。
ダイエットさせたい場合は、獣医師に相談して愛猫に合ったダイエット計画を立てましょう。
猫の肥満は増加傾向にありますが、飼い主の健康管理で防ぐことができるものです。
愛猫が健康で幸せな一生を過ごせるよう、しっかりと配慮してあげましょう!
ここまで読んでくださり、ありがとうございました!