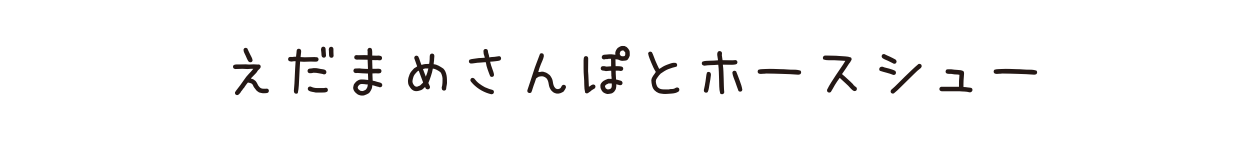人間よりも早いペースで年を取っていく猫。
飼い主さんなら、愛猫には元気で できるだけ長生きしてほしいものですよね。
7歳からシニア期の始まりだと言われている猫ですが、外見の変化があまり見られない場合は、
老化の判断が難しいケースがあります。
とはいえ、愛猫は確実に年を取っていきます。
シニア期の始まりである7歳を期に、普段のお世話の仕方を見直すことで、愛猫の体の負担を減らしできるだけ元気で長生きしてもらえるよう工夫していきましょう!
今回は、シニア期になったら気をつけたいことを中心に、猫の老化のサインも詳しくご紹介します。
猫の7歳はシニア期の始まり|見た目は若くても老化は始まっている

猫の7歳はシニアの始まり、というのは愛猫家さんはご存じのことと思います。
しかし、外見の変化などがあまり見られないことから、7歳を迎えた愛猫に対して「おじいちゃんになったな」「おばあちゃんになったな」とすぐに実感することは、ほとんどないかもしれません。
人間よりも早いスピードで成長する分、猫の老化は思いのほか早くやってきますが、実際に7歳を迎えても 見た目だけではなく動きも食欲も若い猫とほぼ変わらないことが多いと思います。
しかし、個体差はあるものの、猫は7~8歳頃から徐々に体力が落ち始め、代謝や体の機能が低下し始めます。
シニア期に突入した猫にはどんな変化があるのか?元気で長生きしてもらうには、どんなケアが必要なのか?を知っておくことが大切になってきます。
愛猫が元気で楽しい日々を少しでも長く過ごせるように、老化が始まる7歳を期にトイレや食事などのお世話の見直しと、これからの予防と予習を始めましょう!
猫の7歳はシニア期の始まり|まずは食事の見直す

「体は食べ物でできている。」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
猫にとっても、毎日の食事は体の健康を維持するために とても大切なものです。
まずは、食事の見直しを行いましょう。
シニア期の猫は、運動量が減ったり代謝が低下するため、今までと同じフードを食べているとカロリー過多になっていまいます。
シニア猫用に特別に設計されたキャットフードに徐々に変更していきましょう。
最近では、シニア猫用のキャットフードがとても充実しています。
愛猫に合った栄養バランスのフードを選んであげることが大切です。
今の愛猫にどんな栄養が必要なのかは、猫の年齢だけではなく健康状態によっても異なってくるため、
まずはかかりつけの獣医師と相談して、シニア猫用のフードを選ぶのが良いでしょう。
また、腎機能を助け脱水を防止するために、新鮮な水をたくさん飲むことも重要です。
キレイで新鮮な水を、いつでもたくさん飲めるように、愛猫の生活スペースの数ヶ所に水飲み場を設置するなどの工夫をしてあげましょう。
猫の7歳はシニア期の始まり|愛猫の生活環境を見直す

年を取ってくると、運動能力が落ちてくるのは人間も猫も同じです。
猫の体に合わせて生活環境も一工夫してあげることが大切になってきます。
足腰が弱ってきたシニア猫は、トイレをまたぐのも一苦労です。
トイレのふちが浅めのものに変更したり、トイレの入り口にスロープをつけるなどの工夫をしてあげましょう。
動きが鈍くなってトイレに間に合わないような場合は、複数個所にトイレを設置しておくのもオススメです。
また、猫は7歳頃からオシッコの匂いがきつくなる場合があります。
匂いが気になる場合は、愛猫の様子を見て匂いにより配慮した猫砂への変更を検討しても良いと思います。
キャットタワーやキャットウォークを設置しているお家は、その造りも見直してみましょう。
猫は高いところが好きですが、シニアになってくるとその高さが逆に危険な場所になることもあるため注意が必要です。
運動能力の低下で、キャットタワーやキャットウォークに登れなくなったり、逆に降りられなくなったり、降りようと思って落下という危険も考えられます。
段差の低いキャットタワーへの変更や、愛猫が使わないようなら撤去も視野に入れて検討しましょう。
更に、シニア期になると徐々に寒暖差にも適応しづらくなっていきます。
室内温度は、寒すぎず暑すぎないように、一定温度を保つように心がけることも大切です。
猫の7歳はシニア期の始まり|スキンシップを欠かさずに

愛猫とのスキンシップも若い頃に比べてより必要になってきます。
スキンシップを取ることで、老化のサインや体調の変化に気付きやすくなるとともに、猫にとっても良い刺激となるからです。
また、若いうちは頻繁に行う毛繕いも、年を取ってくるとその頻度が落ちてきます。
ブラッシングをして、被毛を清潔に保つお手伝いをしてあげると良いでしょう。
ブラッシングには、被毛の絡まりの予防の他、皮膚を刺激して新陳代謝を促したり血行を良くする働きがあります。
ブラッシングに慣れていない子や苦手な子は、全身を撫でるだけでもOKです。
もし体の汚れが気になる場合は、愛猫の様子を見てシャンプーをしても良いでしょう。
シャンプーが嫌いな子や体が弱っている子の場合は、シャンプーをすると体の負担が大きいので、蒸しタオルで拭いたりシャンプータオルを試してみるのも良いと思います。
便秘の解消や、体の表面(皮膚)の異変に気付くためにも、ブラッシングやマッサージといったスキンシップはとても有効です。
日頃からお腹や胸元あたりにかけて触る習慣をつけると、スキンシップと同時に体調のチェックも行いやすくなるでしょう。
猫の7歳はシニア期の始まり|健康診断で早期発見を

7歳を過ぎたあたりから、半年に1度ほどの頻度で動物病院で健康診断を受けることを おすすめします。
半年に1度というと、多いと感じるかもしれません。
しかし、猫の1年は人間の4年分に相当すると言われています。
半年に1度を、人間で考えてみると「2年に1度」ということになります。
そう考えると、決して多いわけではありません。
また、猫は体調不良を隠そうとする習性があるため、年齢に関係なく病気のサインを見落としがちです。
年を取ってからかかりやすい病気もあるため、通常の健康診断に加えて検査項目の見直しも必要になる場合もあります。
獣医師に相談して、病気の早期発見、早期治療に繋げることが大切です。
猫の7歳はシニア期の始まり|日々の健康チェックも忘れずに

単独行動を好み自由に行動する猫との生活では、飼い主さんが意識していないと体調の変化などに気付かないことが多くなります。
お家でもできる健康チェックを定期的に行い記録しておくことをおすすめします。
お家でできる健康チェック
愛猫の体重を測りましょう。
愛猫を抱っこして体重計に乗り、そこから飼い主さんの体重を引いた数字が猫の体重です。
ジッとできる子であれば、赤ちゃん用の体重計を使ってもOKです。
食事をあげる時は、きちんと量を測ってからにします。
猫が残した場合は、残った分量を量り1回の食事量を算出しましょう。
あらかじめ水の量を測ってから、給水器やウォーターボウルに水を入れると良いです。
容器自体に計量用の目盛が入ったものを使うのも良いと思います。
オシッコや便の回数や量、色などに変化がないかチェックします。
固まるタイプの猫砂を使うと、オシッコの回数や量を把握しやすくなります。
猫は、言葉で体調不良を訴えることができません。
更に猫は、体調不良を隠す傾向にあるので、飼い主さんがこまめにチェックをして、いつもと違わないか早めに気付いてあげることが大切です。
こうした毎日の記録があると、動物病院を受診することになった時も診断の手助けになるでしょう。
ペット用の記録アプリなどを活用すると、日々の記録を手軽に管理できるので便利です。
猫の7歳はシニア期の始まり|オーラルケアも大切

猫の健康を維持するためには、オーラルケアも大切です。
歯磨きをしていない猫は、早くから歯に老化のサインが出てくると言われているのです。
猫は、犬のように口を開けて息をしたり、飼い主さんの顔を舐めることが少ないため、口のニオイに気付きにくく、歯磨きの重要性もまだ浸透していない現状もあるようですが、猫にとっても歯磨きはとても重要な要素。
実は、猫は人よりも歯垢が歯石に変わるスピードが速く、歯磨きをしていないと黄ばんだり茶色くなってくるのです。
そのまま放っておくと、歯周病になり様々な臓器に影響を及ぼすことが考えられています。
さらに、歯周病があると腎臓病の発症が早まる可能性があるというデータもあります。
腎臓病はシニア猫(13歳以上)の猫の約80%近くが発症すると言われていますが、歯周病があるとその発症が3年近く早まると言われています。
大切な愛猫の健康を守るためにも、オーラルケアはとても大切です。
若いうちからオーラルケアを始めれば、猫も抵抗なく慣れてくれやすいでしょう。
歯ブラシや歯磨きに慣れていない猫は、歯磨きシートや歯磨きおやつなどを活用しながら歯磨きの習慣を作ってみるのも一つの手です。

歯みがきおやつグリニーズは、カリカリ好きな猫ちゃんには特におすすめです!
うちの えだまめも食いつき抜群!美味しいみたいです。

さいこーにうまいにゃん
猫の7歳はシニア期の始まり|猫の老化のサイン

シニア期に入った猫には、具体的にどのような変化が見られるのか詳しくご紹介します。
シニア期に入ったとはいえ、見た目にはさほど大きな変化は見られないことが多いですが、よく観察してみると少しずつですが変化が出てきていることに気付くでしょう。
一番分かりやすい変化が、毛並みかもしれません。
猫は毛繕いを丁寧に行い、毛並みを整える動物です。
しかし、シニアになると毛繕いの回数が減り、毛が割れてボソボソになってくるケースが多いです。
これは比較的分かりやすく、気付きやすい老化のサインでしょう。
若い頃は、器用に体を曲げたり足を上げて全身をくまなく毛繕いできていましたが、年を取って関節に痛みが出ている場合は、思うように体勢を作ることができません。
そうなると、だんだん毛繕いの回数が減り毛にツヤがなくなるだけでなく、毛玉状に固まってしまうこともあります。
身体面の変化では、筋肉量の低下などから上下運動をあまり行わなくなり、寝ている時間がグッと増えてくるでしょう。
逆に、睡眠時間が乱れ夜も寝ずに動き回る子もいます。
これは甲状腺機能亢進症の症状ですが、いずれにしてもシニア猫になると若い頃とは違う睡眠の様子が
見られるケースがあることを覚えておくと良いです
さらに、目やにが目立つようになったり、歯周病があれば口臭が強くなるなどの変化が見られます。
食事面の変化では、食べる量が減ることが一般的ですが、逆に食欲が増すケースもあります。
食事の量や水を飲む量が増えているのに、体重が減っていく場合は、代謝にトラブルを抱えていることが考えらえるため、動物病院を受診してみましょう。
生活面では、トイレを失敗することがあるかもしれません。
これは、もしかしたらトイレのフチが高く、運動機能の落ちてきたシニア猫にとってトイレに入りづらくなっていることが原因の場合があります。
また、認知機能にトラブルが出てトイレを失敗してしまうケースも考えられます。
一般的な猫の老化のサインをチェックリストにしてみました。
・目やにがついていることが増えた。
・毛が割れてきたボソボソしてきた。
・毛繕いの回数が減り、毛ヅヤが悪くなってきた。
・毛の色が薄くなったり、顔周りに白髪が増えた。
・高いところに登れなくなったり、着地を失敗することがある。
・筋肉にハリがなく、皮膚が下がってきた。
・食欲が落ちてきた。
・口臭が気になり始めた。
・トイレを失敗することが増えた。
・爪がよく伸びるようになった。
シニア期に入ったからと言って、すぐに上記のような変化が出てくるというわけではありません。
猫の老化は徐々に進んでいきます。
見た目が変わらないからと軽視せず、日頃から愛猫をしっかり観察して、変化がないか毎日チェックすることが大切です。
猫の7歳はシニア期の始まり|シニア猫は病気にかかりやすい

猫がかかりやすい病気として腎臓病が挙げられますが、若い猫に比べてシニア猫はそのリスクが高まります。
猫はもともとあまり水を飲まない動物ですが、シニア猫は のどの渇き鈍感になる傾向があり、更に水を飲む量が減ることも腎臓病のリスクを高める原因と言われています。
腎臓病にかかっている場合、よく水を飲んだり、食欲が落ちてくるといった症状が現れます。
また、オシッコが出なくなったり、逆に量が増える場合もあります。
他に血尿が出たりと、オシッコに異常が現れることが多いでしょう。
トイレ掃除をするときに、オシッコをよく観察することが大切です。
その他に、歯が抜けたり歯周病になったりと、口腔のトラブルも起こりやすいと言われています。
口腔トラブルは食事に直結してくるので、こちらも小さな変化を見逃さないようにすることが大切です。
猫の7歳はシニア期の始まり|さいごに

猫の老化のサインへの気付きは、飼い主さんの観察力にかかっています。
猫の老化には個体差があり、はっきりと何歳からがシニア期で、体に変化が出てきますと言い切ることは難しいです。
ただ、7歳を過ぎたら、いついかなる変化が出てきてもおかしくないと認識していることが大切と言えるでしょう。
シニア期の猫に現れるサインや変化を飼い主さんが認識することで、生活の質をより少ない負担で最良のものにしていくことができます。
それまでの生活に少しの変化と工夫を加えるだけで、シニアになった愛猫がより暮らしやすくなるかもしれません。
生活環境の見直しやフードの見直し、日ごろのケアと気配りで、健康トラブルに早めに気付き対処してあげることはきっと可能です。
愛猫のペースを大切にしながら、こまめに観察して元気なご長寿ライフを目指しましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。