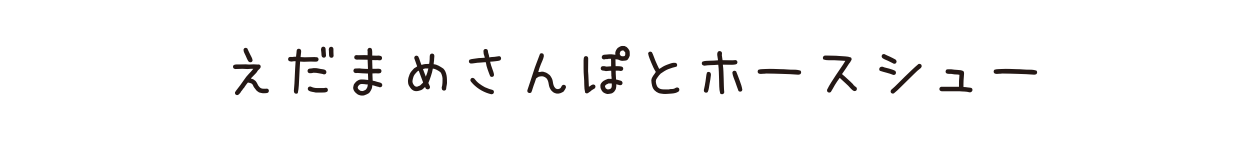災いに合いやすく、忌み慎むべき年齢とされる厄年。
人間には「前厄」「本厄」「後厄」があり、厄払いの祈祷をしてもらう方も多いと思います。
実はこの厄年、猫にも同じような捉え方があります。
厄年を体力的な変わり目と捉え、猫に当てはめるのです。
結論から言うと、猫の厄年は だいたい「7歳」「12歳」「14歳」「17歳」を挙げることができるそうです。
この記事では、猫の厄年にあたる年齢で気をつけたいことを詳しく解説します。
また、猫の厄払いができる神社もご紹介していますので、ご参考までにどうぞ!
猫にもあった「厄年」|厄年とは?

厄年になると厄払いに行く方は多いと思いますが、つまるところ厄年とはどういうものなのでしょうか?
厄年について、少し触れてみたいと思います。
厄年の考え方には古い歴史があり、元々は古代中国から日本に伝わった陰陽道の考え方に影響を受けて生まれたと言われています。
最初にこの考えが入ってきたのは平安時代。
公家の間で広まり、その後 武家や一般市民に広まって行ったと言われています。
江戸時代からはこれが一般化され、今の時代まで続いているそうです。
厄年は「人生で3回ほど訪れる、災難や不幸が降りかかりやすいと考えられている年」のことを差します。
人の人生の中で、体力面や家庭環境的、社会的に機転を迎える年でもあり災厄が起こりやすい時期と捉えられており、よく注意しなければならない年だとされています。
古く平安時代から続く風習のため、厄年は「数え」で計算します。
男性は「25歳」「42歳」「61歳」
女性は「19歳」「33歳」「61歳」とされています。
厄年を体力的な節目だと捉えると、これを猫にも当てはめることができます。
獣医師やブリーダーさんなどが「猫の寿命の節目」と考える年齢が、猫にとっての厄年と言えるでしょう。
猫の寿命の節目といっても、個体差があります。
さらに、猫の厄年の概念は人間の厄年のように、まだ風習として根付いているものではないので、猫の厄年はこの年齢という はっきりとした決まりはありません。
しかし、諸説ある内容をまとめてみると、だいたい「7歳」「12歳」「14歳」「17歳」という年齢を挙げることができるようです。
猫にもあった「厄年」|猫の厄年で気をつけてあげたいこと

では、それぞれの年齢でどんなことに気をつけていけばよいのか。
詳しく解説します!
猫の7歳|健康管理の見直し
猫の7歳は、人間に換算すると約44歳です。
人間では中年ですが、猫にとってはシニア期の始まりと言われています。
見た目は今までとあまり変化はありませんが、代謝や腎臓など目に見えない部分の機能が低下し始める年齢です。
健康診断の頻度を増やしたり、おやつやフードを見直すなど、健康管理を強化していきましょう。
また、年齢を重ねてくると基礎代謝が落ちることや運動量が減ることで、太りやすくなります。
肥満は万病のもとというように、太り気味なことで発症する可能性がある病気もあるため、これまで以上に体重管理が大切になってきます。
シニア期の始まりとはいえ、猫の7歳はまだまだ元気な子も多いです。
遊びたそうにしていたら、しっかりと遊んで運動させてあげましょう!
また、飲水量と排尿量を毎日チェックし、変化を見逃さないようにすることも大切です。
猫の12歳|生活環境の見直し

猫の12歳は、人間に換算すると約64歳に相当します。
10歳を超えてくると、徐々に運動機能が衰えてきます。
猫はもともとよく寝る動物ですが、若い頃に比べると寝ている時間が長くなってきます。
誰にも邪魔されず、ゆっくりと安心して過ごせる寝床を用意してあげると良いでしょう。
また、足腰も弱ってくるので高い場所に登るのも困難になってくる場合があります。
ソファやベッド、トイレなどの脇にスロープを置いたりステップを置いて、上り下りしやくすくてあげると良いです。
他に、食べ物を飲み込む力も徐々に弱くなってきます。
頭を下げた姿勢での食事も辛くなるので、食器を少し高めの台に置いて立った状態で食事ができるようにしたり、食べやすい形状のフードに変更を検討するなど、愛猫の身体面に合わせた生活環境を整えてあげましょう。
食器の位置を高めにするには、食器台を使うこともオススメです。
ケージに取りつけられるフードボウルも良いでしょう。
猫の14歳|体温管理機能が低下してくる
猫の14歳は、人間に換算すると約72歳です。
猫の平均寿命15歳が近くなってくる年齢です。
14歳や15歳を迎えても若々しく元気いっぱいな猫もたくさんいます。
猫種によっても平均寿命は違うと言われているので、老化の度合いも個体差があります。
このくらいの年齢になってくると、体温管理機能が低下してきます。
もともと体温調整が苦手な猫ですが、さらに自分で調整するのが難しくなってくるので、愛猫が暮らす室内温度にも気を遣ってあげたいところです。
蒸し暑い夏や寒い冬を乗り越えられるように、室内温度に気を配りシニア猫が暮らしやすい環境を整えてあげましょう。
また、消化器官が弱くなってくるため、食欲はあってもうまく栄養を取り込めず痩せてくる子もいます。
7歳からシニア期とされ、フードも7歳以上の猫用という扱いになっています。
さらに最近では15歳~という、15歳以上専用のフードも販売されているので、愛猫の様子を見ながらフードの切り替えも検討していきましょう。
更に、腎臓の機能もさらに低下傾向になります。
シニア猫に腎臓病のリスクが高まる理由として、水を飲まなくなるからというのがあります。
猫は元々あまり水を飲まない動物ですが、高齢になってくると動くのが億劫になって、水を飲みに動くことをしない子もいるそうです。
なので、あまり動かなくても水を飲める工夫をしてあげると良いでしょう。
猫の17歳|穏やかな暮らし。介護も視野に入れて

猫の17歳は、人間に換算すると約84歳に相当します。
このくらいの年齢になると、フードを食べる量がさらに減り、寝ている時間がぐっと増えてきます。
とにかく寝ている時間が長いため、フードを食べる量や回数が減ってくるでしょう。
さらに毛繕いの頻度も減るので、若い頃に比べると毛ヅヤも悪くなり、毛並みもパサパサになって割れてきます。
愛猫を触ったときに、毛がパサついてきたなと感じたら、まだまだ元気そうに見えても愛猫の体は着実に老化に向かって変化してきている証拠といえます。
17歳を迎えた猫で注意したいのが認知症です。
認知症は人間同様、なかなか気づいてあげられないことも多くありますが、以下で挙げるポイントを押さえて愛猫をしっかり見てあげましょう。
・夜鳴きをする
・頻繁に鳴く
・落ち着きがなくなる
・トイレを失敗する
・攻撃的になる
・食事のとり方が変わる
・徘徊する
これらの症状は、一つだけ出てくることもあれば、複数が一緒に出てくるケースもあります。
17歳以上の猫で発症することの多い認知症では、食事のとり方に変化が出てくるケースもあります。
いきなり食欲不振になったり、逆に食欲旺盛になったりすることがそれに該当します。
食欲不振であれば飼い主さんが「おかしい」とすぐに気づけますが、食欲旺盛になった場合は気づきにくいものです。
17歳にもなる大切な愛猫がたくさんフードを食べてくれると「元気いっぱい!」と喜ぶのが親心というものではないでしょうか。
しかし、シニア猫がいきなり食欲旺盛になるというのは、認知症以外の病気が隠れている可能性があるため実は危険です。
すぐに動物病院を診察しましょう。
また、このくらいの年齢になると、愛猫が身の回りのことを自分でできなくなってくる場合があります。
そんな時は、飼い主さんがお世話をしてあげることが大切です。
フードを食べさせてあげたり、毛繕いの変わりにブラッシングをしてあげましょう。
粗相が増えてきた場合は、決して怒らずオムツを履かせたり、トイレの数を増やすなどの対策をします。
また、定期的な健康診断も欠かさないようにすることで、病気の早期発見に繋がります。
猫にもあった「厄年」|猫の厄払いができる神社

日本各地には、猫のために厄払いをしてくれるお寺や神社があります。
いくつかご紹介したいと思います。
市谷亀岡八幡宮
個人、法人向けにペットの個別祈祷をしていただける神社です。
祈祷をしていただきたい場合は、予約が必要なので事前に問い合わせをしましょう。
ペットのためのお守りもたくさんの種類があります。
冠稲荷神社冠稲荷神社
ペットのためのペット社殿がある、大きな神社です。
ペットの健康長寿や病気治癒、交通安全だけでなく、縁結びや子宝、安産などを祈祷していただけます。
ペット祈祷は予約となっているので、祈祷していただきたい場合は神社に問い合わせをしましょう。
愛育(めぐし)神社
日本初のペット専用神社です。
参拝は自由にできますが、お祓いや祈祷は完全予約制となっているので、
事前に問い合わせしましょう。
座間神社
ペットたちのための唯一の神社として、平成24年に創建された全国でも珍しいペットのための神社があります。
ペットと一緒に参拝することができる他、ペット用のお守りやペット絵馬も用意されています。
祈祷もしていただけますが、事前に予約しましょう。
少彦名神社
ペットと一緒に1組ずつ祈祷していただける神社です。
ペット専用の絵馬やお守りも多数あります。
祈祷は予約制になっているので、事前に予約が必要です。
神社に問い合わせしましょう。
FAX、電話、メールから予約可能です。
晴明神社
あの有名な陰陽師、安倍晴明を祀る晴明神社でもペットの祈祷をしていただけます。
晴明神社の祈祷は通信制です。
祈祷後、ペット専用の祈願札とお守りを送っていただけます。
ペットと一緒に参拝はできませんし、祈願札やお守りの手渡しも不可な点は注意です。
祈祷の申し込みは公式ホームページの申込フォームから行うことができます。
参拝の際にはマナーを忘れずに。

ペットの祈祷を受け付けている神社ですが、最低限のマナーはきちんと守ることが大切です。
猫の場合、境内での移動にはハーネスよりもキャリーバッグを使用た方が良いでしょう。
各神社の参拝のルールをしっかり確認し、不明なところは事前に問い合わせをしておくと当日 安心して参拝することができます。
ペット同伴を許可してくれているとはいえ、他の参拝者に迷惑をかけないように心がけることも大切です。
参拝のルールやマナーをしっかり守って、ご祈祷していただきましょう!
猫にもあった「厄年」|さいごに

厄年には科学的な根拠がないという捉え方もありますが、年齢を重ねるとともに体の機能が低下してきたり、健康管理を見直したりと、生活環境を見直すための一つの目安としてうまく活用できる風習といえるのではないでしょうか。
この風習を愛猫へ応用し、愛猫に少しでも長く健やかに快適に暮らしてもらいたいものですね。
愛猫の長生きの秘訣は、飼い主さんのケアが影響してくる部分も大きいです。
猫の体調変化の節目となる厄年をうまく活用して、日々の健康管理や生活環境の見直しに役立ててみてください!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。