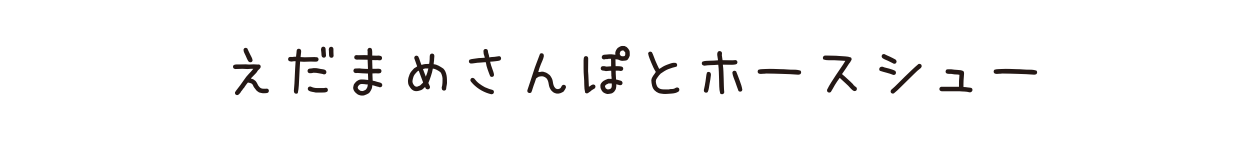猫の体に小さな白い粉のようなものがついていたら、それは「フケ」かもしれません。
猫も人と同じようにフケが出ます。
少量であれば問題ありませんが、脱毛があったり、痒みがある場合は皮膚病の可能性があります。
今回は「猫のフケ」について、対策方法も合わせて詳しく解説します!
猫の体に白い粉?!|ある日のまめ

ある日、こちらに背中を向けている まめを見ていて気付いた違和感。
よく見ないと気付かないものでしたが…

背中(尻尾の付け根あたり)に、何やら白い粉のようなものがついているのを発見しました。
パパッと手で払うとすぐに取れて、まめの様子にかわったところはなく、ゴミでもついていたのかな?と思っていたのですが、暫くするとまた同じような場所に白い粉を発見。

それをよく観察してふと思ったこと。

これって…もしかしてフケ?
猫の体に白い粉?!|そもそもフケって何?

フケは、古くなって剥がれた皮膚の角質のことをいいます。
猫のフケが出るのは、人と同じで新陳代謝によって出てくるものです。
皮膚が新たに生まれ変わるタイミングで、古くなって剥がれ落ちた角質が「フケ」となって表面に現れます。
これは、皮膚が正常に代謝している証拠です。
黒猫などの毛色が濃い猫は、白いフケが目立つこともありますが、新陳代謝によって出てくるものなので、少量であれば何の問題もありません。
しかし、全身にたくさんのフケが見られたり、猫が痒がっていたり、シャンプーをしてもフケが出続けるなどの場合は、何らかの皮膚トラブルの可能性があるため注意が必要です。
猫の体に白い粉?!|フケの原因は?

猫の皮膚の生まれ変わるタイミング(ターンオーバー)は、約3週間といわれています。
少量のフケであれば生理的な現象なので心配いりませんが、量が増えたり、体を執拗に掻いている
場合は、何らかのトラブルが起こっている可能性が考えられます。
以下のような場合は、ケアをしてフケ対策をしてあげることが大切です。
猫のフケの原因|乾燥
空気が乾燥していると皮膚も乾燥し、フケが出やすくなります。
完全室内飼いの場合は、エアコンの乾いた空気の影響で皮膚が乾燥することが考えられるため、乾燥しやすい冬場だけではなく、エアコンを使っている時間が長い夏場も気をつける必要があります。
加湿器を使用したり、毛にスプレーする保湿剤などで皮膚の乾燥を防ぐようにケアしてあげましょう。
猫のフケの原因|ストレス
猫のフケはストレスが原因で増えることもあります。
猫はストレスを感じやすい動物なので、気持ちを落ち着かせるために過剰に毛づくろいを行い、それが結果として皮膚炎を患いフケが増えるというケースもあります。
また、ストレスホルモン自体がフケを増やす原因に繋がることがあるため、猫の生活環境を見直して、ストレスの軽減をしてあげることが大切です。
家の近所に工事現場があったり、引っ越しをして生活環境に変化が出たときなど、特に注意してあげましょう。
猫のフケの原因|スキンケアのし過ぎ/スキンケア不足

猫は日頃からよく毛づくろいをして自分の体のケアをする動物です。
通常は、毛づくろいのときにフケも一緒にケアができているので目立ちませんが、毛づくろいをあまりしない猫の場合は、フケが体に残り目立ちやすくなることがあります。
また、高齢になってあまり動かなくなってきた猫や、猫の舌が届きにくい背中などはフケが目立つでしょう。
そのような場合は、飼い主さんがブラッシングをしてケアしてあげてください。
ただし、過剰なブラッシングや強めにブラシをあててしまうと、その刺激によって皮膚の新陳代謝が過剰になってしまい、フケが増える原因になるので適度な強さと頻度でケアしてあげましょう!
猫のフケの原因|加齢
人と同じように、猫も歳を重ねてくると皮脂の分泌が減ってきます。
皮膚の油分が減ってくると、水分が奪われ皮膚が乾燥しやすい状態になり、フケの原因になります。
高齢の猫は、乾燥肌になりやすいので日頃からよく観察して、乾燥を防ぐために保湿してあげたり、必要であれば動物病院に相談することも大切です。
猫のフケの原因|栄養の偏り
栄養が不足していたり、おやつばかりを食べていて栄養が偏っていたり、キャットフードが体に合わなかったりすると、フケが多く出てしまう原因になります。
栄養素の偏りが猫の皮膚の健康に必要な栄養不足を招き、フケを増やしてしまいます。
主食は、栄養バランスの整っている総合栄養食を与え、毎日バランスの良い食事を心がけてあげましょう。
そのうえで、猫の皮膚の状態を確認しながら、他に必要なものがあるのか検討をすると良いでしょう。
猫の体に白い粉?!|猫のフケは病気の可能性もある

猫のフケには、病気が原因となってフケが増えるケースも考えられます。
皮膚トラブルの他にも、内臓疾患が隠れている場合もあるので、猫の行動や体調の変化にも気を配る必要があります。
過剰なフケが見られる場合は、以下のような病気を患っている可能性があるため気になることがあったら、早めに動物病院を受診しましょう。
アレルギー性皮膚炎
アレルギーによる皮膚炎で、猫のフケが増える場合があります。
食べ物に含まれる成分に反応する食物アレルギーやノミの唾液に反応するノミアレルギー、花粉などの環境中のアレルゲンに反応するアトピー性皮膚炎などが原因でフケが増えることがあります。
アレルギー性皮膚炎は、痒みが一般的な症状で、ひどくなると脱毛や大量のフケが見られます。
痒みが強い場合は、患部を執拗に舐めたり、噛んだり、掻きむしり血がにじむ場合もあるでしょう。
猫にそのような症状が見られる場合は、一度 動物病院を受診しましょう。
今まで、健康で何事もなかった猫でも突然アレルギーを発症することがあるので、日頃から愛猫の様子をよく観察することが大切です。
寄生虫による皮膚炎
ノミやダニ、シラミなどが猫の体に付着すると、その唾液などから皮膚炎を起こしフケが増えるケース
があります。
ネコショウセンコウヒゼンダニが寄生することで発症する「疥癬(かいせん)」という皮膚炎は、激しい痒みを訴えることが多く、皮膚には発疹やフケ、かさぶたが見られます。
主に、耳や肘、かかと、お腹などに症状が出やすいものです。
また、ヒセンダニによる疥癬は、人獣共通感染症なので人にも感染します。
飼い主さんも十分に注意が必要です。
ツメダニが寄生することで発症するのが「ツメダニ症」です。
ツメダニに寄生された部分からは、大量にフケが出たり、湿疹ができ脱毛が見られます。
しかし、猫自身はあまり痒がらないという特徴があります。
このツメダニも人に感染します。
人がツメダニに感染すると、強い痒みのと痛みが出るので注意してください!
疥癬もツメダニ症も、ダニ駆除薬を投与して治療を行うのが一般的ですが、他の猫にも感染するものなので多頭飼いしている場合は同時に全ての猫に駆除薬を投与したり、マットやベッドなど、猫が使っているもの全てを清潔にして寄生虫を追い出すことが大切です。
皮膚糸状菌症
皮膚糸状菌症は、「猫カビ」ともいわれています。
猫の皮膚に常在する「皮膚糸状菌」というカビの一種が原因で発症します。
温度や湿度が高くなることで菌が繁殖し、猫の免疫力の低下や不衛生な生活環境などが原因で皮膚病を引き起こします。
皮膚糸状菌症は、感染しても最初は猫自身はそれほど痒がりません。
主な症状は、耳の周辺や手や足などに円形の脱毛が見られて発症がわかる場合がほとんどです。
小さな円形から脱毛部分が広くなっていき、大量のフケが発生します。
悪化すると、発疹やかさぶたが見られます。
治療方法は、外用薬や抗真菌剤を含むシャンプーなどですが、猫の住環境も殺菌が必要になります。
猫のベッドやマットなど、洗えるものは漂白剤を使って殺菌するようにしましょう。
皮膚糸状菌症は、菌をもっている猫との直接的な接触や、感染した毛やフケとの接触などで感染します。
母子感染も多いため、発症の大半が子猫の時期が多いでしょう。
菌をもっている猫がいる場合は、触ることで感染する可能性が十分にあるので、多頭飼いしている場合は同居猫や飼い主さん自身も感染には注意が必要です。
内臓疾患の可能性
大量のフケは皮膚の新陳代謝が変わったサインでもあります。
皮膚や被毛の状態は、猫の栄養状態の鏡と言っていいでしょう。
慢性腎臓病や糖尿病、慢性腸炎などがあると、多飲多尿の症状だけではなく「毛艶が悪い」「フケが多い」「毛が油っぽくベタベタする」などの症状が見られることがあります。
普段から猫の様子をしっかり観察して、気になることがあったら早めに動物病院へ相談しましょう。
猫の体に白い粉?!|猫のフケの対策と予防法

感染症やアレルギーなど何らかの病気が疑われる場合や、大量のフケが出ているときは、まずは動物病院を受診して獣医師に相談してみましょう。
病気だった場合、対処方法を間違えてしまうと治らないどころか、病状が進行することもあるため、自己判断せずしっかりとフケの原因を突き止めてから次の対処に進むことが大切です。
また、日頃から猫のフケが出にくくなるように、飼い主さんがケアしてあげることも大切です。
自宅でできるフケの対策と予防方法をご紹介します。
猫のフケの対策と予防法|ブラッシングをする
愛猫に行うブラッシングは、出てきているフケの対策やフケが出ないようにする予防対策に効果的です。
長毛種の猫の場合は、毎日のブラッシングが欠かせないでしょう。
猫用のブラシで全身を優しくブラッシングしてあげましょう。
力を入れてゴシゴシ行うと、皮膚に刺激を与え逆にフケが大量に出てしまう原因になりますし、皮膚炎を引き起こす原因にもなるので注意が必要です。
また、ブラッシングが苦手な猫も少なくありません。
短い時間で数回に分けてブラッシングをするなど工夫してあげましょう。
ブラシは、愛猫の毛の長さや毛量、毛質に応じて選びます。
コームや長毛猫用ブラシ、短毛猫用ブラシなど、飼い主さん自身も使いやすいと感じるものを選ぶとブラッシングしやすくなるでしょう。
また、静電気が起きにくく、皮膚への刺激が少ないブラシもおすすめです。
猫のフケの対策と予防法|シャンプーをする

シャンプーを嫌がらない、もしくは慣れている猫の場合は、フケの対策と予防として効果的です。
長毛種の猫の場合は、コンディショナーを一緒に使うと毛がほつれにくくなり、毛玉の予防にもなります。
使用するシャンプーは、猫用のものを選びます。
フケが気になるときにシャンプーする場合は、刺激の少ないシャンプーを選ぶのが良いです。
また、皮膚のバリア機能を強化するために、保湿効果のある猫用シャンプーやコンディショナーでも
効果的です。
皮膚にトラブルがあるときは、獣医師に相談してシャンプーを選んでもらうのが良いでしょう。
シャンプーのしすぎは、皮膚の油分を奪う恐れがあるので頻度は1~2ヶ月に1回程度で良いです。
また、シャンプーはしっかり洗い流すことがポイントです。
シャンプー剤が体に付着したままだと、皮膚トラブルの原因となってしまいます。
そしてシャンプーの後に、しっかりと乾かしてあげるのも大切なポイントです。
濡れたままや湿ったまま放置すると、雑菌が繁殖してフケが出てきてしまいます。
猫のフケの対策と予防法|加湿をする
皮膚が乾燥していると、角質が剥がれやすくなりフケが増えます。
空気が乾燥している季節やエアコンを使って室内が乾燥しているときは、加湿器で湿度の調節を行いましょう。
猫に保湿用のスプレーを使ったり、蒸しタオルを使って皮膚の潤いを保つのも良いでしょう。
室内を加湿して適度に湿度調整をすることで、乾燥から猫の皮膚を守り、ウイルスの活性化も抑えることができます。
猫のフケの対策と予防法|食事を見直す
与えているキャットフードの栄養素が、猫の体質に合わないとフケが増えることがあります。
食事に含まれる栄養素の約30%が、猫の皮膚の栄養となります。
おやつをたくさん与えて栄養の偏りがあったり、猫の体質に合わないキャットフードを与えていると、
皮膚に十分な栄養がいかず、フケが増えてしまいます。
そのため、食事を見直すことによって猫のフケの対策と予防に効果が期待できます。
獣医師に相談しながら、キャットフードを変えてみるのも良いでしょう。
猫のフケの対策と予防法|ストレスを軽減する
ストレスは猫の免疫力を弱めてしまい、皮膚トラブルの原因になる場合があります。
飼い主さんと遊ぶ時間が足りない場合や、来客、引っ越しなど、猫がストレスを感じる原因は様々あります。
引っ越しや新しく猫を迎えるなど、生活環境に大きな変化が訪れる場合は、猫が安心して身を隠せる場所を準備してあげたり、新しい猫との生活環境を分けたりと工夫してあげることが大切です。
1日に数分でも、おもちゃを使って遊ぶ時間を作ってあげることで、運動不足解消に繋がるのはもちろんのこと、飼い主さんと愛猫の触れ合う大切な時間となります。
愛情不足でストレスを感じる猫もいるため、愛猫と触れ合う時間を作ってあげましょう。
また、キャットタワーを設置してあげると運動不足に効果的です。
猫の体に白い粉?!|猫のフケのケア用品

猫のフケの対策をするときは、ブラシをはじめとするケア用品を使用してみるのも効果的な方法です。
猫のフケのケア用品|抜け毛をとり自然な艶を出すブラシ
静電気防止機能付きで猫がブラッシングを嫌がらないように作られてる猫用のブラシです。
遠赤外線効果のある天然鉱石が配合されており、抜け毛をとりながら猫の毛を美しく保ってくれる優れもの。
ブラシ部分は、ソフトクッションタイプで、猫の皮膚にも優しい設計です。
現在は、中・長毛種の猫用ブラシとして販売されていますが、猫壱さん曰く短毛種の猫でもブラッシングは可能とのコメントを頂いております。
短毛種の猫の場合は、毛質が硬めの猫の方が抜け毛が取れやすいとのことです。
猫のフケのケア用品|マルットペット シャンプー
天然由来100%で、なおかつ香料0%で完全無香料のシャンプーです。
香料が苦手な猫には良いですね。
また、毛や皮膚に優しいアミノ酸系のシャンプーで、フケ対策には大切な保湿力も高いという特徴があります。
着色料・香料だけでなく、石油系界面活性剤やシリコン、アルコールも使われていない、ペットにとても優しいシャンプーです。
肌や嗅覚が敏感なペットの負担を減らすため、最低限の成分のみが厳選されたペットのためのシンプルなシャンプーとなっています。
猫のフケのケア用品|自然流トリートメントシャンプー スーパーグレード
3~15倍に薄めて使うタイプのシャンプーです。
52種類の和・漢・洋・ハーブ・植物エキス配合で、保湿効果と洗浄力が高く肌に優しいシャンプー。
天然素材系のみで作られており、合成香料や着色料などは添加していないのが魅力的です。
毛がもつれやすい長毛種の猫には特にオススメされています。
猫のフケのケア用品|ペットキレイ 皮フを守るリンスインシャンプー 猫用
100%植物生まれの洗浄成分を使った、猫の肌に優しいリンスインシャンプーです。
泡立ちや泡切れが良く、毛や皮膚についた汚れや臭いをしっかり洗い流してくれます。
弱酸性で無着色、微香性なのも良いポイントです。
また、ペットショップやホームセンターなどでも購入できるので、飼い主さん的にはお買い物しやすいのではないでしょうか。
低刺激なシャンプーを探していたり、香りが欲しいけど控えめなものが良いという場合に適しています。
猫のフケのケア用品|PN 水のいらないニャンコの泡シャン
洗い流さずふき取るだけの泡シャンプーです。
猫がグルーミングをして体を舐めることを前提として、合成界面活性剤・合成保存料は使わずに作られています。
フコイダン・オリーブスクワラン・ベタイン・トレハロースという、4種の天然保湿成分を配合をしているため、フケの原因になる乾燥を防ぎ予防効果が期待できます。
香料も使われていないので、体に香りがつくことを嫌がる猫にもぴったりでしょう。
猫のフケのケア用品|ピュアラ スキンコンディショニング
フルーツや野菜エキスをベースに、皮膚のターンオーバーを助ける無添加の保湿スプレーです。
乾燥や痒みがみられる皮膚トラブルの軽減に薦められています。
猫の皮膚を乾燥から守り、保湿してくれるのでフケ予防に効果が期待できます。
また、シャンプーが苦手な猫にも良いでしょう。
猫のフケのケア用品|WAFONA 猫用 オールインワンスプレー
お手入れ、保湿、スキンケアができる猫用のオールインワンスプレーです。
界面活性剤やアルコール、合成香料などは使われておらず、安心・安全に作られています。
108種類の天然植物エキスと52種類の植物酵素、純水を配合し、自然由来の力で愛猫の健康を維持するサポートをしてくれます。
フケ予防の保湿だけではなく、顔周りのケアや静電気の予防もできる優れもの。
シャンプーが苦手な猫でもぴったりですね。
猫の体に白い粉?!|さいごに

猫のフケは日常生活を送るなかで、自然と出てくるものです。
しかし、場合によっては何らかの皮膚トラブルや病気を知らせるサインの可能性もあります。
猫の体にフケを発見しても、自宅で様子を見ていいものか、動物病院の受診が必要なものか、その判断は難しいものです。
猫は体調不良を隠す傾向があり、飼い主さんが日頃から意識して観察してあげることが大切です。
動物病院を受診するかどうかのポイントは
- 全身にフケが出ている
- 頻繁に体を掻いている
- 毛艶が悪くなってきた
- 体調が悪そうに見える
- ブラッシングやシャンプーをしてもたくさんフケが出てくる
- キャットフードを変えてもフケが出てくる
といった症状が見られる場合は、一度 動物病院を受診しましょう。
皮膚のトラブルが出始めると、猫の行動に変化が出てきます。
家での行動は獣医師には分からないため、何か様子がいつもと違うなと感じたら、飼い主さんのその感覚は間違いありません。
猫が体調の変化をきたしている兆候なので、獣医師に相談してみましょう。
今回は、猫の体に白い粉?!猫のフケについて詳しく解説しました。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!